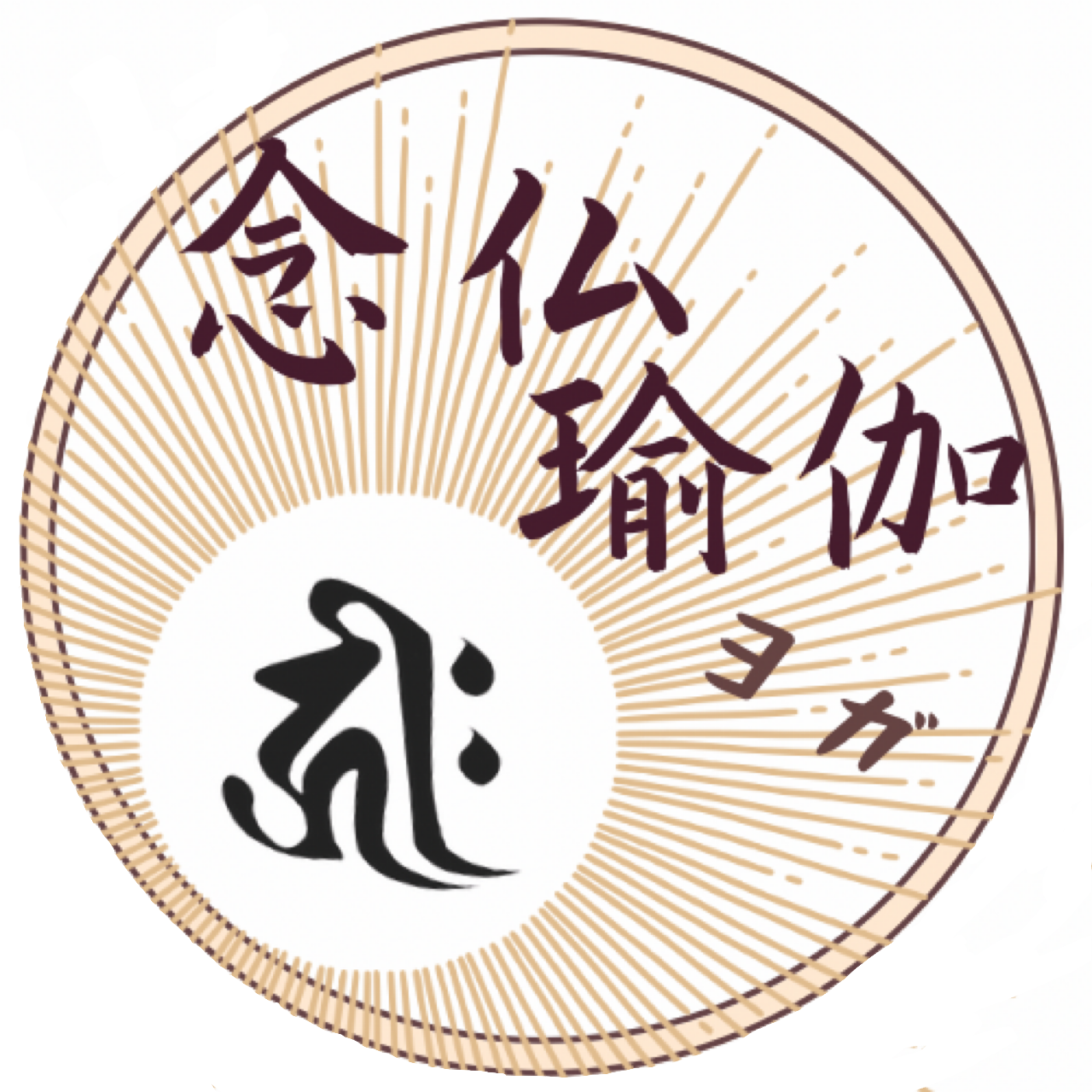開放型実践仏教寺院へ
当たり前のことを当たり前のこととして実践することの何と難しいことでしょうか。
正光寺でのあらゆる活動は実践仏教としての価値があります。掃除一つとってもそれは単なる作業ではなく、内観をしてこれからの人生を心身共に穏やかに生きていくための仏道修行となるのです。これは至極当然のことであると同時に、当然の事を実践するのがとても難しいことを私たちは知っています。私たちは単に知っているだけでなく、実践すること、行動することに努めなければなりません。
正光寺は原点に立ち返り、すべての活動が仏道修行として内観・念仏したい人たちに提供されるべきものであるということを再認識し、檀信徒ばかりでなく少しでも多くの人たちに最大限価値の提供をしていきたいと考えています。それが正光寺本来の役目だからです。しかし、正光寺が本来の役目を果たして社会へ貢献していくためには、多くの人の力が必要です。
和合の精神に基づいて多くの人の力を集約した集団を【正光寺サンガ(僧伽:saṃgha)】とし、正光寺として社会へ価値を最大限提供していきます。
サンガとは「集団」や「組合」を意味するサンスクリット語で、仏教では出家者の集まりである「僧団」の意で使われてきた言葉です。正光寺が仏教の和合精神で社会貢献していく集まりであることから、サンガという言葉を使うことにしました。
大学連携の価値
社会人が価値を創出し、学生は勉強するもの、という棲み分けに意味がないことは周知のとおりです。実践こそ最大の学習だからです。実践を最重要視する正光寺では、学生に積極的に実践の場を提供すると共に、開放型実践仏教寺院としての活動に力を貸してもらいたいと考えています。
また、単にひとつの大学、ひとつのゼミとのみ連携するのではなく複数の大学、複数のゼミと連携することを想定しています。学生にとって自らの大学以外の価値観や能力を共有できる点でさらなる価値を享受することができると考えています。
もちろん連携するのは学生だけではなく、アクティブシニアや子育て世代、法人組織も含まれるため、就活はもちろん。世代間交流による多様な価値観を認め合い、共に生きることの大切さとその実践にも通じるものとなります。
学生がこの活動に関わることは、社会に出て主体的に社会貢献をしていくことができる人財になるための土台を築くことに繋がるのです。
アクティブシニア連携の価値
人生百年時代といわれて久しくなりました。見た目はもちろん、体力的にもシニア世代とは思えない方も多く見られます。私たちは彼らから学ぶべき事、力を借りるべきことが沢山あります。特に文化の伝承者としての経験値は大いに活かされるべきです。
そもそもアクティブシニアという分類をする必要さえありません。自分ができる範囲で皆、社会に貢献すればよいのです。ただそれだけのことです。
社会貢献は生きる喜びとなります。活動に関わり続けることが充実した毎日を過ごす上でとても大切な事なのです。
子育て世代連携の価値
子育ては生物の営みの基本です。それを担ってくれている世代との関わりは、社会全体として子どもを育てていこうという共生意識の向上に欠かすことができません。
社会全体として「我が子」のように育てていこうという純粋な精神を高めていくためには仏教による内観・念仏活動がとても効果的です。
法人組織との連携の価値
社業そのものが社会貢献であるという事はもはや前提とされ、その上でさらなる社会貢献が求められる時代に私たちはいます。それを負担と理解するのではなく、寧ろチャンスと理解するべきであり、社業と絡めて価値の創出と提供をしている法人があらゆる業界で台頭してきています。
このような活動に法人組織が関わることによって、学生に成長の機会を、子育て世代に安心して子育てできる環境を、アクティブシニアに活躍の場を、社会の文化水準の向上をもたらすのです。
法人組織との連携の価値
社業そのものが社会貢献であるという事はもはや前提とされ、その上でさらなる社会貢献が求められる時代に私たちはいます。それを負担と理解するのではなく、寧ろチャンスと理解するべきであり、社業と絡めて価値の創出と提供をしている法人があらゆる業界で台頭してきています。
このような活動に法人組織が関わることによって、学生に成長の機会を、子育て世代に安心して子育てできる環境を、アクティブシニアに活躍の場を、社会の文化水準の向上をもたらすのです。
異文化によって知る日本の文化的価値
日本にはこのような仏教を内包したすばらしい文化があるにも関わらず、日本人の多くが自分たちの文化的価値を過小評価しています。多くの日本人が日本の文化価値として理解しているものは、京都や奈良をはじめとする名所だけです。外国人をはじめとする日本文化を詳しく知らない人にとっては、日本の街並み一つとっても異国情緒あふれる魅力的な文化そのものなのです。どこにでもある町寺だって同じことです。私たちにとっては当たり前の価値こそが日本の深淵な魅力であり、私たちはあらゆる日本的体験を内外に知らしめていく責務があるのです。それこそがいつの時代にも行われてきた押しつけではない《素朴な布教≒広報・PR》の有り方のひとつだと考えます。
正光寺というお寺を運営する私たちには、価値ある仏教文化に根ざした当たり前の日常を国内外に発信し体験し理解してもらうことで、開放型実践仏教寺院への変貌をとげる責務があると考えています。
正光寺サンガ(僧伽:saṃgha)が形成されるということは、すなわち想いが形になりつつあるという事の証左なのです。
食によって知る生命尊重と日本の文化的価値
食は育てる事にはじまり、収穫して調理し、皆で食べる事までを含みます。しかし、多くの人は収穫を体験しません。調理を体験しない人もいます。ただ出てきたものを食べるだけ。下手をすれば一人で食べる。すべてが悪いとは言いません。ただ、折に触れて原点に立ち返り、食を育てる事、収穫すること、調理すること、皆で食べる事を実践する必要があります。なぜならば、日々の忙しさや環境によって、心の底から感謝をするという事を忘れてしまいがちになるからです。
食べ物を育てる事の大変さ、収穫した時の喜び、調理次第で美味しくなることの驚き、皆で食べる事の楽しさ。そういった心の躍動が私たちには必要なのです。日本人は古来から素晴らしい自然の中で、そうした心を大切にしてきたのです。
私たちにはそのような「日本人の美しい心」「共に生きる心」を後世に、あるいは世の中に伝承して知らしめていく責務があるのです。
内観とは何か
内観とは一体何でしょうか。それは、日々の生活に忙殺されるあまり、ないがしろにしてしまいがちな物事の本質や大切なことを再確認することです。
なぜ、再確認と言うのでしょうか。それは、生きていれば自然と触れていく大切なことや本質的なことに気づかない、気づいても忘れている、覚えていても実践することができていないからです。それらを思い出す、つまり再確認をして実践することを目的とするからです。
内観は一人で行っても良いでしょう。精神力、集中力を高め深い思考活動をすることができるからです。皆で向き合っても良いでしょう。和合の精神に基づき喜び分かち合う中で多くの気づきや再確認ができるからです。
内観は継続させることが大切です。なぜなら、日々の生活に忙殺されて内観したことを忘れたり、おざなりにしてしまったりするからです。
内観して再確認することの多くは、とても単純で当たり前とされている事ばかりです。にもかかわらず実践し続けるのが難しいことばかりです。
実践できないということは、単に知っているだけで理解していないということです。私たちは、内観によって、知っている状態から理解している状態にし、それを維持し続けることが大切なのです。それが内観です。
目的
お寺でのあらゆる活動を内観と念仏に通じる仏道修行として人々に提供し、心身の調和・和顔愛語を実現。
活動
- 心の掃除活動による内観(営繕)
落ち葉掃き・水撒き・除草・大掃除・御身拭・窓ふき・トイレ掃除・池・水盤といった掃除に関わる活動を通じて心を静め、自身を内省(大切な事、本質的な事を再確認する行為)して以降の日々を心身共に穏やかに過ごすことができるようにする実践仏教
- 自然との対話による内観(植樹・剪定・管理)
植栽と向き合い、自然の有様を目の当たりにする活動を通じて心を静め、自身を内省(大切な事、本質的な事を再確認する行為)して以降の日々を心身共に穏やかに過ごすことができるようにする実践仏教
- 祈りの聖地 諸仏に魂を入れるのは人間
そこにある聖なるものへ何を祈るのか、その環境整備と実践。子育て地蔵などの各種尊像との対話を通じて心を静め、自身を内省(大切な事、本質的な事を再確認する行為)して以降の日々を心身共に穏やかに過ごすことができるようにする実践仏教
- 伝統行事 体験による内観(儀式・儀礼)
施餓鬼・彼岸などの行事、写経会、月例供養会といった伝統的な行事を通じて心を静めて自身を内観し、以降の日々を心身共に穏やかに過ごすことができるようにする実践仏教
- 仏 具 簡易的環境による内観
私たちは一定の環境を整えないと内観するのが難しい。お守りひとつでも有るのとないのとでは心の持ちようが違うことが沢山ある。内観を補助するための仏具を頼りとして、以降の日々を心身共に穏やかに過ごすことができるようにする実践仏教。(ここではもはや「縁起物」ではなく「仏具」と理解する)
- 半斎供養 命との対話による内観(精進料理体験など)
半斎供養とは生命に対する感謝、命を頂くことに対する感謝をすることです。それを儀式化したものが半斎供養です。命に対する感謝を前提として、皆で食事を共にする事、食を活かすことを通じた内省活動を行います。
- 宿 坊 滞在による内観(日常体験)
その場所で生きている人たちの目線で得られる体験を重視する人たちに対して、伝統的な価値を提供していきます。故に整った快適環境に価値を置くのではなく、徹底した体験価値を提供していきます。