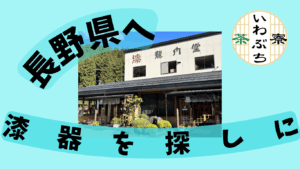いわぶち茶寮の器を求めて ― 木曽・龍門堂さんを訪ねて ―
正光寺の境内にある寺カフェ「いわぶち茶寮」では、開店以来、日本の伝統文化を大切にしながら、お客様に心落ち着くひとときをお届けしてきました。そうした歩みの中で、日々のもてなしにふさわしい器を探していたところ、長野県木曽地方で木曽漆器の技を受け継ぐ老舗「龍門堂」さんに出会いました。
木曽漆器のぬくもりに出会う
木曽地方は、豊かな森林と清らかな水に恵まれた土地。古くから漆器づくりが盛んで、400年以上にわたり、生活の中で育まれてきた伝統工芸の里です。
木曽漆器の特徴は、木の美しさを活かす技法と、堅牢で長く使える実用性。
職人の手で木地を作り、漆を何度も塗り重ねて仕上げることで、使うほどに艶が増し、温もりが深まっていきます。
木曽漆器には、特に代表的な三つの技法があります。
1.木曽春慶(きそしゅんけい)
木曽を代表する技法のひとつで、木地に下地を付けず、生漆を何度も擦り込みながら仕上げる手法です。木目そのものの美しさを前面に出すことで、自然のぬくもりと漆の光沢が共存します。光の加減で浮かび上がる木目は、まるで木が呼吸しているような優しさを感じさせてくれます。
2.木曽堆朱(きそついしゅ)
色漆を何層にも塗り重ね、表面を研ぎ出すことで、下の色が斑模様となって現れる技法です。複雑な色の重なりが深みのある風合いを生み出し、見る角度によって異なる表情を楽しめます。長く使うほどに艶が増し、時を重ねるごとに味わいが深まっていく――そんな魅力をもつ漆器です。
3.塗分呂色塗(ぬりわけろいろぬり)
複数の色漆を用いて模様や文様を描き、最後に丹念に磨き上げて仕上げる技法。幾何学模様や優雅な色分けが特徴で、華やかさと上品さを併せ持ちます。装飾性が高く、暮らしの中に伝統美を取り入れたい方にも人気のある塗り方です。
このように、木曽漆器にはさまざまな表現の幅があり、どの技法にも職人の誇りと丁寧な手仕事が息づいています。
龍門堂さんで感じた、手仕事の力
龍門堂さんの店内に入ると、木の良い香りがふんわりと漂い、心がすっと静まります。
棚には、木目の美しい器が整然と並び、ひとつひとつに異なる表情があります。
奥には職人さんの工房があり、静かな空気の中に漆を磨く音がかすかに響いていました。
手に取ると、驚くほど軽く、手のひらにすっと馴染みます。漆の艶やかさと木の柔らかな手触りが心地よく、まさに“手仕事のぬくもり”を感じました。
やさしい店長さんとの出会い
応対してくださった店長さんは、とても穏やかで、こちらの話を丁寧に聞いてくださいました。「お寺のカフェで使いたい」とお伝えすると、器の形や色味、漆の種類まで、いくつも提案してくださいました。
「漆器は高級なものという印象があるかもしれませんが、もっと日常の中で使ってほしいんです」という言葉が印象的でした。
伝統を守りながらも、現代の暮らしに寄り添う姿勢――その柔軟さが龍門堂さんの魅力なのだと感じました。
“キッチンうるし”という新しい挑戦
特に心惹かれたのが、食洗機対応の「キッチンうるし」シリーズ。
漆器は繊細で扱いにくいというイメージがありますが、このシリーズは現代の暮らしに合わせて改良されています。水や熱にも強く、毎日の食卓でも安心して使えるのです。
たくさんの方お出しする場所にこそ、こうした漆器の柔軟さが活きると感じました。伝統の美しさを守りつつ、今の暮らしに寄り添う新しい漆器のかたち。それは、まさに「文化を今に生かす」ものづくりだと感じます。
憧れの器をいわぶち茶寮へ
どの器も丁寧に作られ、価格にも相応の価値を感じます。一つひとつが職人さんの手仕事であり、長く使うほどに味わいが増していく。まさに“一生もの”の器です。
いわぶち茶寮では、お客様にコーヒーやお食事をお出しするたびに、器の美しさも楽しんでいただけるよう心がけています。今回選んだ漆器が、これからの時間をより温かく、豊かなものにしてくれると信じています。
まとめ
木曽の自然と人の手のぬくもりに触れながら、
「日本の伝統文化を日常に生かす」という原点を改めて感じた旅でした。【いわぶち茶寮 × 龍門堂】
静けさとぬくもり、伝統と現代。
この出会いが、これからのおもてなしをさらに深めてくれそうです。